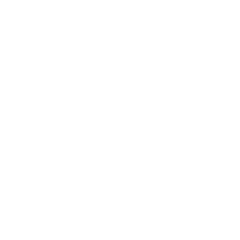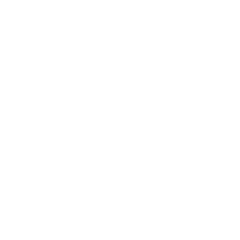小学生の睡眠時間、足りてますか?
〜育児中の親御さんに届けたい、ぐっすり眠るためのコツ〜
こんにちは。
私には小学2年生の娘がおりますが、お子さんの毎日を見守る中で、こんなふうに感じることはありませんか?
「朝なかなか起きられない…」
「学校から帰るとすぐ眠そう」
「夜の寝つきが悪くて困る…」
実は、これらの原因は「睡眠時間が足りていない」というサインかもしれません。
🕰 小学生に必要な睡眠時間はどれくらい?
日本小児保健協会やアメリカ睡眠医学会の指針によると、
7〜12歳(小学校低学年〜中学年)のお子さんには、9〜11時間の睡眠が推奨されています。
つまり、夜9時までに寝て、朝6〜7時に起きるくらいのリズムが理想です。
| 年齢 | 推奨睡眠時間 |
|---|---|
| 6〜13歳 | 9〜11時間 |
| 小学2年生 | 約10時間が目安 |
🌙 睡眠が足りないとどうなるの?
睡眠不足が続くと、こんな影響が出てくることがあります。
- 集中力が続かない
- イライラしやすい、気分が不安定になる
- 学力や記憶力の低下
- 免疫力の低下や体調不良
- 成長ホルモンの分泌が減少 → 身体の成長に影響
大人と違い、子どもは「眠たい」とは言わずに機嫌が悪くなることも多いみたいです。
🏡 帰宅後から就寝までの理想的な過ごし方
例えば、午後3時半頃に帰宅する小学生の場合、こんなリズムが理想です:
| 時間 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 15:30 | 帰宅・おやつ | 甘すぎない軽食が◎ |
| 16:00 | 宿題や学習 | 短時間集中でOK |
| 17:00 | 外遊びや自由時間 | 体を動かすと寝つきも良くなる |
| 18:00 | 夕食 | 家族での会話が心の栄養に |
| 18:30 | お風呂 | ぬるめのお湯でリラックス |
| 19:00 | 読書・静かな時間 | スマホやテレビは控えめに |
| 20:00 | 就寝準備 | 歯みがき・おやすみのあいさつ |
| 20:30 | 就寝 | ぐっすりおやすみなさい 🌙 |
📱 寝つきが悪い時の対処法
- テレビやスマホは寝る2時間前までに
- お風呂は寝る1時間前までに済ませると◎
- 寝る前は部屋を暗くして、静かな雰囲気に
- 読み聞かせや軽いストレッチもおすすめ
🍀 最後に
子どもの眠りは、心と体を育てる大切な「栄養」です。
「早く寝かせたいけど、バタバタしてて難しい…」
「お友だちの家庭と違って不安…」
私も自営業だとなかなか思うようにいかないことが多いですが、一日中完璧じゃなくても大丈夫。
できる日から、できる範囲で少しずつ整えていけば、子どもも自然とリズムを掴んでいきましょう。
大人も子どもも、夜ぐっすり眠って、毎日を気持ちよくスタートできるといいですね。