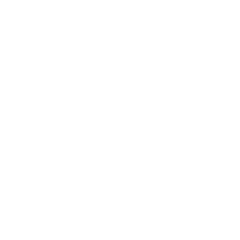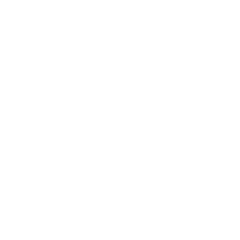本日はかんたんにお彼岸について…。
お彼岸とは
「彼岸(ひがん)」と言うのは、対岸、つまり「あちら側」のことです。
対する「此岸(しがん)」と言うのは、「こちら側」になります。
でも、こちら側とかあちら側と言うのは一体何のことでしょう?
実は、彼岸と言う言葉は、サンスクリット語の「波羅密多(はらみた)」の意訳。
「波羅蜜多」には「成就する」「完成する」という意味があり、仏教では悟りの境地に達することを表す言葉です。
つまり彼岸とは直訳すれば、「あちら側」・「成就(完成)する」といった意味となります。
到彼岸(とうひがん)」とは
文字通り「彼岸」に到ること。
私たちの生きている迷いのある世界「此岸(この世)」から、迷いのない世界、悟りの境地「彼岸(ひがん)」に到達するためには、「修行」が必要です。修行で乗り越えるべき煩悩と迷いを川にたとえ、川のこちら側が「この世」、あちら側は「悟りの境地」と言うわけです。

お彼岸は日本固有の行事
冒頭で述べたように、もともと仏教に由来する「お彼岸」。
でも、実は他の仏教国には見られない日本固有の行事です。
煩悩と悩みに満ちた現世「此岸」に対し、悟りの境地を指す言葉であった「彼岸」は、いつしか死後の「極楽浄土」ととらえられるようになります。
亡くなったご先祖さまの住む世界も「彼岸」とされるようになったのです。
「春分の日」と「秋分の日」(※)には、太陽が真東から昇って真西に沈みます。
昼と夜の長さがほぼ同じになるこの日に、日本では彼岸と此岸がもっとも通じやすくなると考えられたため、ご先祖様を供養するようになりました。
この習慣が今に続き、お彼岸にはお寺で「彼岸会法要」が行われたり、「お墓参り」に行くなど、日本独自で発達した「ご先祖様をしのぶ文化」となっています。
お彼岸はどのようにして迎えたら良いのか?
お彼岸をどのように迎えたら良いのか、といった質問をちょうだいします。
お彼岸当日は、お墓参りやお寺の法要行事だけでなく、ご家庭のお仏壇やお仏具をきれいにお掃除しましょう。
最後に
彼岸は「日願(ひがん)」に由来する、との説もあります。
恵みをもたらしてくれる太陽を信仰したり、ご先祖様を大切にする気持ちは、日本に限らず古来より普遍的なものと言えますね。
※「春分の日」「秋分の日」は、国民祝日に関する法律で規定されています。(具体的に月日は明記されてません)
ちなみに国立天文学台が、毎年2月に翌年の「春分の日」「秋分の日」を官報で公表しています。
投稿内容について、ご意見、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お問い合わせはこちら